
ストーマがあっても、基本的に食事の制限はありません。
ここでは、食事について心がけておくと良いことを紹介します。
- 食事は規則正しい時間にとり、よく噛んで食べましょう。
- 体形が変化することにより、今まで使用していた装具が使えなくなる場合があります。食べすぎには注意しましょう。
- 栄養バランスの良い食事を心がけましょう。食品の種類や食べる量によって、ストーマから出るガスや排泄物の量やにおいが変わることがあります。
- 食事は楽しくとりましょう。ストレスや悩み、不安などにより食べ物の消化が悪くなることがあります。
※腎臓病や糖尿病、高血圧などで医師から食事療法を指示されている方は、その指示を守ってください。
消化不良・下痢
下痢をしたときには一度に食べすぎず、様子を見ながら少しずつ食べるようにします。下痢をすると脱水症状を起こしやすいので、十分な水分補給と消化の良い食事を心がけましょう。
下痢がひどい場合は、消化吸収の良いおかゆやよく煮たうどんなどから始め、少しずつ普通の食事へ戻していくと良いでしょう。なお、数日たっても下痢が治まらない場合は、かかりつけの医師に相談してください。
消化の良い食品
(消化不良・下痢のときに食べると良い食品)
 米飯(おかゆや重湯)
米飯(おかゆや重湯)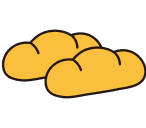 パン
パン よく煮たうどん
よく煮たうどん くず湯
くず湯 よく煮て裏ごししたほうれんそう
よく煮て裏ごししたほうれんそう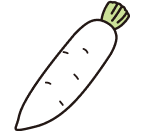 だいこん
だいこん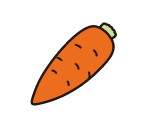 にんじん
にんじん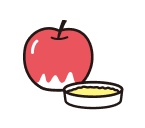 すりおろしたリンゴ
すりおろしたリンゴ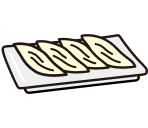 ささみ
ささみ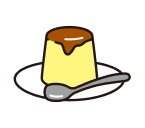 プリン
プリン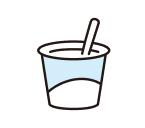 ヨーグルト
ヨーグルト
この他には... 白身の煮魚、じゃがいも、ビスケットなど
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
便がやわらかくなりやすい食品
(消化不良・下痢のときに避けた方が良い食品)
 ビール
ビール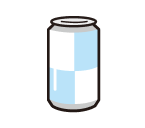 お酒
お酒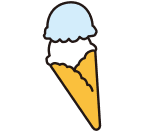 アイスクリーム
アイスクリーム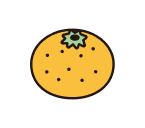 果物
果物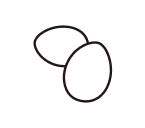 生卵
生卵
消化の悪い食品
(消化不良・下痢のときに避けた方が良い食品)
 海藻類
海藻類 きのこ類
きのこ類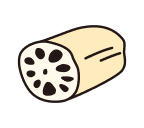 れんこん
れんこん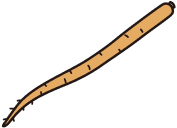 ごぼう
ごぼう たけのこ
たけのこ
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
 調理や食べ方での工夫
調理や食べ方での工夫
消化に悪いとされる食品も、細かく刻んだりよく噛んで食べたりすることで消化しやすくなります。
便秘
便秘にならないように、規則正しい生活と適度な運動を心がけましょう。食事は3食きちんととり、水分を十分に補給することが大切です。また、ストレスが便の性状に影響することもあります。
なお、便秘が続く場合は自分の判断で薬を飲まず、医師に相談してください。
繊維を多く含む食品・整腸作用のある食品
(便秘のときに食べると良い食品)
 麦
麦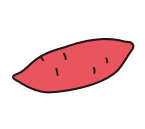 さつまいも
さつまいも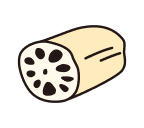 れんこん
れんこん きのこ類
きのこ類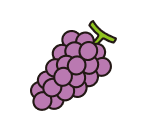 ぶどう
ぶどう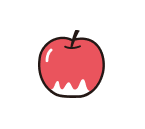 りんご
りんご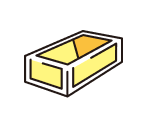 バター
バター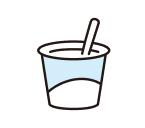 ヨーグルト
ヨーグルト
この他には... 野菜、ごぼう、果物(もも、バナナなど)、豆類、海藻類、酢の物、乳酸飲料など
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
 食事や排便の記録について
食事や排便の記録について
食事の内容や食事をした時間帯、その後排便のあった時間や便の性状を日々記録することで、自分に合った食事を見つけていくのも良いでしょう。
ガス・におい
ガス(おなら)の発生は、食事のときに飲み込んでいる空気が主な原因です。
話をしながら食事をしたり、すするような食べ方をすると口から空気を吸い込みやすく、ガスが多くなります。
また、食べ物によってはガスを発生させやすいものやにおいの原因になりやすいものもあります。
逆に、ヨーグルトや納豆などには整腸作用があり、ガスやにおいを抑える働きがあります。
ガスを発生させやすい食品
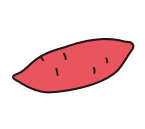 さつまいも
さつまいも カリフラワー
カリフラワー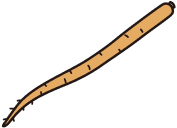 ごぼう
ごぼう きゃべつ
きゃべつ 枝豆
枝豆 エビ
エビ ラーメン
ラーメン
ガスの発生を抑える食品
 パセリ
パセリ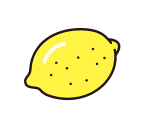 レモン
レモン 乳酸飲料
乳酸飲料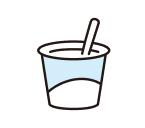 ヨーグルト
ヨーグルト
においが強くなる食品
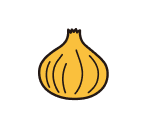 たまねぎ
たまねぎ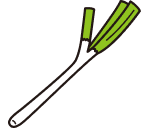 ねぎ
ねぎ にら
にら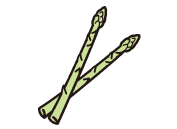 アスパラガス
アスパラガス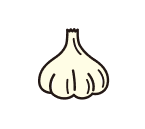 にんにく
にんにく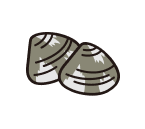 貝類
貝類 カニ
カニ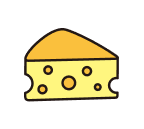 チーズ
チーズ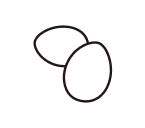 卵
卵
においを抑える食品
 オレンジジュース
オレンジジュース クランベリージュース
クランベリージュース 乳酸飲料
乳酸飲料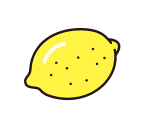 レモン
レモン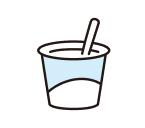 ヨーグルト
ヨーグルト
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
 お酒やたばこについて
お酒やたばこについて
お酒は飲んでもかまいません。ただし、飲みすぎると下痢や脱水症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。たばこを吸う習慣のある方は、たばこを吸うときに空気を吸い込むことでガスが多くなりますので、たばこの量を減らしてみると良いでしょう。
- 食事は規則正しい時間にとり、よく噛んで食べましょう。
- 体形が変化することにより、今まで使用していた装具が使えなくなる場合があります。食べすぎには注意しましょう。
- 栄養バランスの良い食事を心がけましょう。食品の種類や食べる量によって、ストーマから出るガスや排泄物の量やにおいが変わることがあります。
- 食事は楽しくとりましょう。ストレスや悩み、不安などにより食べ物の消化が悪くなることがあります。
※腎臓病や糖尿病、高血圧などで医師から食事療法を指示されている方は、その指示を守ってください。
繊維の多い食べ物は、便が詰まることがあるので、一度に食べすぎないようにしましょう。また、このようなものは細かく刻み、よく噛んで食べるように心がけましょう。便の排泄量が多いときは、脱水症状が起こり体がだるくなりやすいため、スポーツドリンクや水などを補給しましょう。
便が詰まりやすい食品
 とうもろこし
とうもろこし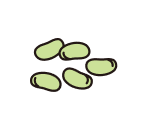 豆類
豆類 きのこ類
きのこ類 ブロッコリー
ブロッコリー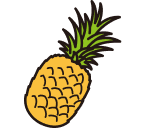 パイナップル
パイナップル 玄米
玄米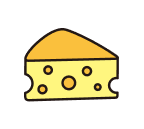 チーズ
チーズ
この他には... 海藻類、ポップコーンなど
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
 お酒やたばこについて
お酒やたばこについて
お酒は飲んでもかまいません。ただし、飲みすぎると下痢や脱水症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。たばこを吸う習慣のある方は、たばこを吸うときに空気を吸い込むことでガスが多くなりますので、たばこの量を減らしてみると良いでしょう。
- 食事は規則正しい時間にとり、よく噛んで食べましょう。
- 体形が変化することにより、今まで使用していた装具が使えなくなる場合があります。食べすぎには注意しましょう。
- 栄養バランスの良い食事を心がけましょう。食品の種類や食べる量によって、排泄物の量やにおいが変わることがあります。
- 食事は楽しくとりましょう。ストレスや悩み、不安などにより食べ物の消化が悪くなることがあります。
※腎臓病や糖尿病、高血圧などで医師から食事療法を指示されている方は、その指示を守ってください。
におい・尿路感染
水分の摂取量が少ないと、尿路感染を引き起こしやすく、尿のにおいも強くなりやすいです。そのため、1日の尿量が1,500~2,000mLくらいになるように、十分に水分をとりましょう。また、尿の細菌増殖を抑える働きのあるビタミンCを多く含む食品をとることも、尿路感染や尿臭の予防につながります。ただし、糖分を多く含む食品もあるので、糖尿病やカロリー制限のある方は医師や看護師に相談してください。
尿臭が強くなりやすい食品
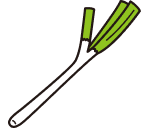 ねぎ
ねぎ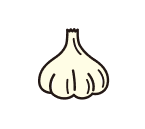 にんにく
にんにく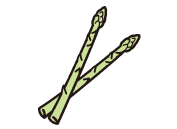 アスパラガス
アスパラガス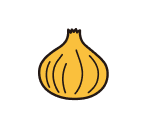 たまねぎ
たまねぎ
尿臭を抑える食品
 パセリ
パセリ アセロラジュース
アセロラジュース クランベリージュース
クランベリージュース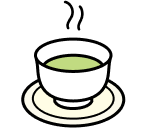 緑茶
緑茶
※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。
 お酒やたばこについて
お酒やたばこについて
お酒は飲んでもかまいません。ただし、飲みすぎると下痢や脱水症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。たばこを吸う習慣のある方は、たばこを吸うときに空気を吸い込むことでガスが多くなりますので、たばこの量を減らしてみると良いでしょう。

